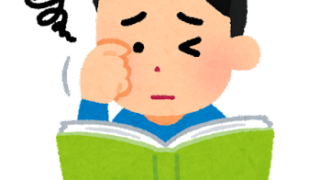「休む」ってむずかしい。でも、ちゃんと休まなくてもいい。
1 溜まった疲れ

ここ最近「疲れたなぁ」と感じる。朝起きたときから「なんか今日疲れてるな」と思うし、仕事をしててもすぐに「疲れた」と一休みしている。
確かにここ1ヵ月は怒涛だった。裁判の判決が出て、取材対応をして、これからのアクションも考える日々だった。一方でライターの仕事もこなす。そして自分の将来も考えなくてはと思っていたので、人からアドバイスをもらったりしていた。そんな疲れが溜まってきたのだろうと思う。
2 「今日は休み!」でも体がうごいてしまう

昨日は休むはずだった。祝日だし、コワーキングスペースも休み。「それなら今日はしっかり休もう」と思っていた。
出だしは上々。朝から湯船に浸かり、ゆったりと考え事をする。ふと「古本屋巡りでもするか」と思い立ち、11時ごろには家を出る。近くのBOOKOFFへ行き、ぼーっとしながら、目に入った本を手に取る。前から読みたかった本も、「これ今読みたいかも」という本も見つかった。仕事関連で探す予定だった社会的養護に関する本もあった。合計6冊ほど購入し、ほくほくとした気分だった。
「別の古本屋も探してみるか」。そう思い立つと、体が自然と動き出す。電車で20分ほど移動し、大きなBOOKOFFへ行く。そこでも6冊ほど購入し、また別のBOOKOFFへと行く。気づいたら家を出て5時間以上経っていた。買った本の大半は仕事関連の本。「あれ、なんかほとんど仕事してないか?」と身体の疲労を感じながら思った。
そして今日も「今日こそ休む!」はずだった。家でぐだぐだするのもなんだなと思い、コワーキングスペースで気ままに過ごすかと移動。「コワーキング行くなら、昨日買った本持っていくか」と10冊弱持っていく。気づくと、ペラペラと仕事関連の本を眺め、気づいたら仕事をしていた。「あれ?休めてなくない?」
3 「休む」って案外むずかしい

以前こんな記事を書いた。

本によると、私達は「休み方」をこれまで学ぶ機会がなかったようである。「運動」「睡眠」「食事」については学校でも教えられてきたけれど、「休む」「休養」「休日の過ごし方」といったことについては、私達は手探りでやってきた。でもなかなか休めているようで、休めていない。だからこそ、記事の中でも書いた本が売れているのだろう。
また私の場合、個人事業・ライターという職業柄もあるかもしれない。個人事業の場合、働こうとすれば働けてしまう。意識的に休みを作ることが大切ではある。一方でライターという仕事は私の趣味である読書とも密接に関わるし、「書く」「読む」は生活の一部でもある。仕事・趣味・生活がにじみ合っている生き方をしているのも、完全に「休む」ことが難しい要因なんだと思う。
でも、悪くない生き方だなと思う。
4 大切なのは「ちゃんと休まなきゃ」という強迫観念から離れること

昔から私は「休む」ことが苦手だった。学生時代「休む」ことに対して罪悪感があった。でも、今の「休む」ことができない原因はそこじゃないと思う。「ちゃんと休まなきゃいけない」という強迫観念のようなものが私にはあると思う。
私は疲れ切ったあとに休まざるを得ない時間が苦手だ。特に夕方から夜の睡眠までの時間、そして昨日今日のような休日が、私はあまり得意ではない。「ちゃんと休まなきゃ」とすごく焦るのだ。スマホ・パソコンは見ない。家でじっとして体力を回復させる。とにかくぼーっとする。それができないと「休めていない」ように感じるのだ。
でも思う。「休まなきゃ」と力むこと自体が、もう「休み」から遠ざかっているのではないか、と。
5 自分なりの「休み方」がある

そう考えると、「休み」の時間に疲労してしまっても、身体が自然にそうやって動いた結果なのであれば、それがいいのではないかと思う。だからBOOKOFFで本を探し回って疲れても、今こうやって休み中にブログ記事を書いていたとしても、自然に身体がそう動いているのであれば、いいのではないかと覆う。
「やらないといけない」ではなく、自分から自然に生まれた身体の動きであることが大切だと思う。そして不思議なことに、私の場合こうして文章を書いてくると、自分自身が回復していくような感覚がある。今の私にしか書けない言葉が、ふと現れてくる。自然に文章を書きたいと思った結果、自然に言葉が生まれてきた。その感覚がとても私は好きだ。「休まない」「休む」の曖昧な境界にある感覚を、私は大切にしたい。
身体の自然な流れに身を任せることが、私にとっては「休み」なのだと思う。ここは論理や理性というよりは、直感で感覚的なものだと思う。その直感や感覚、感性を育てていくことが、きっともっと自然に「休む」ことにつながるとおもっている。