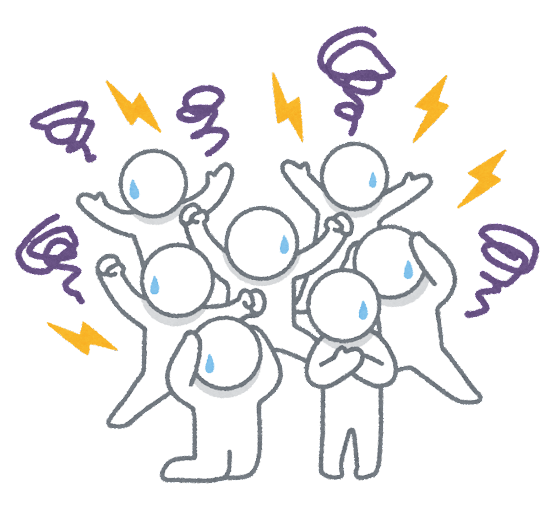【患者の様子を「聴く」のではなく「訊く」ということ】

ふと思った当たり前のこと。
以下何を言いたかったか3つにまとめると
・そこには3つの「きく」が重要になること。
・中でも医者は「訊く」ことが重要になってくる
ということだったかなと。
1.患者の語りの不安定さ
私の主治医に限ったことではないと思うが、医者は「体調はどうですか?」と尋ねることが多いと思う。
ここから医者は患者の状況を把握する。
もちろんその時の話す様子からも伺うのであろうが、
その瞬間の時の様子でしかない。
だとすれば、例えば1~2週間に一度の診療なら、
その間の様子は患者にしかわからない。
つまり、診療の際に患者が語らなければ、医者はその間の様子を把握できないことになる。
しかし、患者は必ずしもその1週間2週間の間の様子を、全体的に述べる力が、病気によって弱まっていくことは十分考えられる。
その時、患者から語られる言葉は、今日はどうだったか、そういえばなんとなく一週間こんな感じだったという印象ベースの語りになりうる。
そうした、印象ベースの語りを基にして、医者が薬を処方したり、なんらかの見通しを立てることは、かなり危ういのではないか、と思う。
2.「きく」ということ
その時医者に求められる力は「きく」力だろう。
しかし、それは
話が耳からなんとなく入ってくる「聞く」(hear)でも、
相手の話に集中して耳を傾ける「聴く」(listen)だけでは、
不十分なように思える。
そこには、
質問を重ねていく「訊く」(ask)という行為が不可欠ではないだろうか。
患者の症状は、正直いって患者にしかほとんどのことがわからない、という姿勢をもっと医者が持っているべきなのかもしれない。
2~3分で終わる診療は、医者は診察していないことがほとんどだ。もしそれで症状を回復させていけるのなら、患者に語る力・伝える力があるからだ。医者ではなく、むしろ患者が自分でアセスメントをして、ただそれに基づいて医者は薬を出しているだけなのだ。
逆に10分~15分の診療時間があっても、医者がただひらすら話を聞きながしているのであれば、それは果たして診察と言えるだろうか。そこで回復する患者は、むしろ話すことで自分自身の整理ができる力がある患者なのではないか。
また共感して「聴く」(listenやactive listening)ことも、
医者としては不可欠な部分でもあるが、十分な行為ではない。
やはりそこで回復する患者は、自分自身の病を自分自身で乗り越える力があるのであり、それを手助けする意味では医者の共感は重要ではあるのかもしれない。
しかし、自分自身で自分の状況を把握することが難しい、
自分で自分のことを語る力が弱まっている患者に対して、
ただひたすら共感するだけでは、医者の仕事としては十分とは言えないのではないか。
3.医者の専門性としての「訊く」こと
医者の仕事とは、この三つの「きく」(hear, listen, ask)の、
「訊く」(ask)の部分を普段よりも比重多くすることではないのだろうか。そしてその「訊く」とは、医学などの専門分野に基づいた、アセスメントに必要な行為なのである。だからこそ、医者には専門性があるとされるべきなのではないか。医者の専門性は決して薬を出すだけではないはずだ。
要するに医者としての「きく」姿勢というのは以下だろうと思う。
①まず生きていれば自然な「聞く」ことがあり、しばしば集中できずに「聞く」ことがあるのはしょうがない。
②しかし、基本的なベースになるのは、共感的に「聴く」ことなのではある。だが、ひたすら話を聴くだけでは、患者の語る力に頼りすぎている面がある。
③そこで医学などの専門領域に基づいた、とにかく質問をすることで「訊く」ことが重要なのであろう。
4.蛇足
ちなみに「きく」と漢字変換をすると、様々な「きく」が出てくるが、中でも「掬(キク)」という変換もあることに気づく。これは、手で掬いとるなどにも使われる漢字である。しかし、もう一歩「きく」から付け加えた「掬する」と動詞形になると、「事情を推測する」や「趣を感じ、楽しむ」という意味となる。
「きく」ことから、もう一歩進むことで、受動的な「きく」というあり方から、自分自身もまた楽しむことができるくらい、相手の事情を慮ることができるようになるということなのかもしれない。